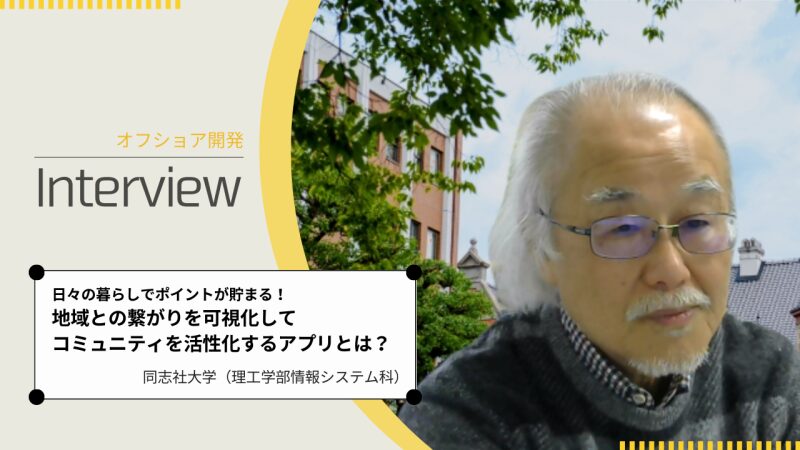
| 導入前の課題 |
★ 地域活動の見える化と参加促進を両立したい
|
| 選んだ理由 |
★ 実現イメージの共有と共創の提案が決め手に
|
| 導入後の成果 |
★ 地域のつながりが可視化、学生のスキル向上にも貢献
|
我々の研究テーマは「コミュニティシステムデザイン」というもので、地域コミュニティを研究の対象としています。アプリの名称であるCSDはこの「Community Systems Design」の略です。
そして今回、バイタリフィアジアには、CSDアプリという地域コミュニティを繋ぐためのアプリとそのデータを集めるためのクラウドサーバーの開発を行なっていただきました。
システムというのはシステムを構成する要素と要素同士の関係性で定義されていて、システムとして一つの機能や目的を達成しようとすることで成り立っています。サッカーに例えて話すと、メンバーが要素、チームの連携プレーが関係性と言うことができます。
チームのパフォーマンスは目に見えるメンバー(要素)だけではなく、メンバー同士の目に見えない連携プレー(関係性)で良さが決まりますよね。企業などの組織も、社員と社員同士の関係性や、各々が属する部署同士の連携で成り立っているため同様にシステムと呼ぶことができます。
我々は地域コミュニティもこれと同じようにシステムとして捉えていて、地域コミュニティを良くしていくには、住んでいる人々同士の連携や繋がりを大事にしていく必要があると考えています。企業の場合には目的が共有され、対価ももらっているため「一つの目的を達成すること」を目指しやすいシステムである一方、地域コミュニティは家族構成も世代も価値観も考え方も違う人たちがたまたまそこに住んでいて、特別なにか目的を共有しているわけではありません。
比較的薄い関係のシステムだと考えています。このシステムにおいて繋がりを強化し広げていくことが地域コミュニティを良くすることに繋がるのでは、という考えから今回のCSDアプリの開発プロジェクトがスタートしました。
我々は学生主体でアプリの仕組みを考えていくのですが、どうしても抜けが出てきてしまいます。バイタリフィ社はその点プロフェッショナルな方々なので、実装するためのアルゴリズムやメカニズムを細かく提案していただきました。
我々の学科の学生たちもプログラミングを学んでいる学生たちです。しかし、大きなシステムかつ多くの人たちに満足して使ってもらえるようなソフトウェアやプログラムを作り上げるまでのレベルには至っていません。
この部分をバイタリフィ社にお願いしているのですが、学生たちも技術を磨きたいという意欲を持っているので、彼らの勉強も並行して行えるようにサポートしていただきました。開発環境を共有してもらってプログラムの中身を理解したり、バイタリフィ社の技術者の方に質問して答えてもらったりですね。とてもありがたかったです。
現在バージョン3までリリースしていますが、フィールド実験を行いながら徐々にいいものが出来上がってきていると思います。
我々が動作検証した段階では問題なかったものの、使う方の多くがご年配の方ということもあり、実際に出来上がったアプリを使ってもらうと想定していなかった使い方をされることが多くありました。例えば「戻る」ボタンとして置いていた矢印がそもそも何の矢印なのかわからず、他のボタンを押してしまう、メールアドレスの登録に手間取ってしまう、などです。
フィールド実験を経て、機能を取捨選択したり、ブラッシュアップしたりしながら現在も一緒に改良を進めているところです。
またプログラムについての細かな質問については先ほど言ったように随時質問させてもらっていたのですが、全体が見えていない、分かっていないことを痛感したので開発を行うにあたっての全体の構造や枠組みについての理解を深めたいと思い、講義をお願いしました。
具体的には、クライアント・サーバー型のシステムをどのようなフレームワークでどのように開発するのか、今回使用したクラウドであるAWSをどのように使っているのかといった内容です。中身のソースコードなどを分析するにあたってもまずは全体のことがわかっていないと先に進めないので、講義を実施していただいたことで大変勉強になりました。
もちろん、研究テーマ内で数値的な効果があり、フィールド実験で実際に地域のみなさんの活動がデータとして出てくるので、アプリを通じて行動の分析や仕掛けに対する効果計測などができています。学生たちも卒業論文や修士論文、学会発表の論文などでデータを活用できています。
今回、特にバイタリフィアジア社のNhi(ニー)さんと頻繁に連絡をとっていたのですが、うまく連携して開発ができたなという印象です。我々の基本設計やアプリの仕様書の抜けの部分を指摘していただいたり、逆提案をしていただいたりと、“依頼側” と “依頼される側” という関係性ではなく、「一緒に考えて開発していく」という姿勢がすごくいいなと思いました。
今後も一緒に開発をしていってくれることが我々にとっては何よりもありがたいので、この関係性を続けていけたらと思っています。
「まだ依頼するか決めていない」「要件がはっきりしていない」といった段階でも問題ありません。
弊社でのソフトウェア開発の進め方や体制のご相談など、少しでも気になることがあれば、お気軽にご連絡ください。

櫻井 岳幸
Managing Director
開発予算や要件以上に「どうやって開発後の成功に近づけるか」をお客様と一緒に考えます。まずはご相談ください!